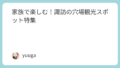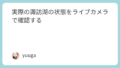次回の諏訪大社の御柱祭は2028年、令和10年です。
諏訪大社大総代は2025/04/04に日程を発表しました、山出しは上社が4/1~3で下社が4/8~10です。
里曳きは上社が5/3~5で下社が5/12~14日です。
前回は諸情勢の影響で山出しを史上初のトレーラーでの運搬でしが今回は人力での曳行や木落をします。
御柱祭で次はいつですか!開催日程詳細

2028年御柱祭の開催日と場所
| 諏訪大社御柱祭 | イベント | 月日 |
|---|---|---|
| 上社 | 山出し | 4月1日(土)、2日(日)、3日(月) |
| 上社 | 里曳き | 5月3日(水)、4日(木)、5日(金)※ゴールデンウィーク期間 |
| —— | ———- | ——- |
| 下社 | 山出し | 4月8日(土)、9日(日)、10日(月) |
| 下社 | 里曳き | 5月12日(金)、13日(土)、14日(日) |
| 下社 | 仮見立て | 2025年5月12日(月)、※予備日 5月13日(火) |
御柱祭は長野県の諏訪地域に根付いた壮大な神事であり、7年に一度という特別な周期で開催されます。
これは単なる地域のお祭りではなく、千年以上の歴史を持つ重要な伝統行事であり、諏訪大社を中心とする信仰の文化と深く結びついています。
次回の開催は2028年に予定されており、上社(本宮・前宮)と下社(春宮・秋宮)でそれぞれのスケジュールに沿って実施されます。
通常であれば、上社・下社ともに春に祭事が集中して行われ、最初に行われる「山出し」は4月、続いて「里曳き」が5月に行われるのが通例です。
これらの行事では、巨大な御柱が山から神社へと運ばれ、多くの氏子や見物客でにぎわいます。
正式な開催日程や詳細なスケジュールについては、諏訪大社および各関係機関からの正式発表を待って確認する必要があります。
御柱祭とは?読み方、その歴史と意義
御柱祭の読み方は(おんばしらさい)です。
この御柱祭は長野県の諏訪大社の神域に新たな御柱(ご神木)を建てるために行われる壮大な神事です。
神様に新たな住まいを提供するという神聖な意味を持ち、諏訪地域に住む人々の信仰心と生活に深く根ざしています。
平安時代から千年以上にわたって受け継がれてきたとされるこの行事は、単なる伝統ではなく、地域の歴史そのものを象徴する重要な文化財でもあります。
御柱には巨大なモミの木が使用され、それを山の中から切り出して曳き出すところから祭りが始まります。
木を山から運び出す「山出し」では、険しい山道を多くの氏子たちが力を合わせて進みます。
その後、町中を通って神社まで運ぶ「里曳き」が行われ、地域の結束力が試される一大イベントとなります。
このような勇壮な曳行の様子や、伝統衣装を身にまとった参加者の姿は、国内外からの見物客を惹きつけ、観光資源としての魅力も高まっています。
御柱祭は信仰と文化、地域の誇りが融合した特別な行事として、多くの人々の関心と参加を集めているのです。
諏訪大社における御柱祭の役割
御柱祭は、単なる賑やかな祭りではなく、神社と地域住民との間に深く根差した信仰の象徴であり、地域社会の精神的な絆を再確認する重要な機会でもあります。
諏訪大社は上社(本宮・前宮)と下社(春宮・秋宮)の四社で構成されており、それぞれに4本ずつ、合計で16本の御柱が建てられます。
これらの御柱は、神域を囲むようにして配置されることで神聖な空間を確保し、神々の御座所を新たに清めるという宗教的な意味合いを持ちます。
この神事は、神様との新たな契約を結び直し、地域に生きる人々の無病息災や五穀豊穣、商売繁盛など、様々な願いを込めて執り行われるものです。
また、御柱を曳く時は木やり唄に併せて協力一致で力を合わせて御柱を引っ張るのは、世代を超えた交流と絆が深まり、地域の一体感が一層強まることも大きな特徴です。
こうした文化的・宗教的背景があるからこそ、御柱祭は何世代にもわたって大切に守られてきたのです。
御柱祭の神事とその進行
曳き行事のスケジュールと参加方法
曳き行事は、御柱を山から神社へ運ぶ大規模な行進です。日程は地区によって異なりますが、数日間にわたって行われます。
参加には事前登録が必要な場合もあり、安全講習を受けることが推奨されます。
各地区の役割と責任について
各地区には、御柱の伐採・運搬・建て付けなど様々な役割が割り当てられます。
地区ごとに編成される「綱元」や「木遣り」などのチームがそれぞれの任務を遂行します。
信仰と祭りが交差する瞬間
御柱祭のハイライトは、曳き行事のクライマックス「木落とし」です。急斜面を御柱が滑り落ちる様子は迫力満点であり、神聖さと人間の勇気が交差する瞬間です。
御柱祭における「やってはいけないこと」
注意すべき行動と安全対策
御柱祭は多くの人が参加するため、安全確保が最優先です。危険行為や無理な参加は禁止されており、指定された装備や指示に従う必要があります。
地域コミュニティとの協力の重要性
地元住民との協調なくして御柱祭の成功はあり得ません。外部からの参加者も、地元のルールや伝統を尊重する姿勢が求められます。
過去の事故とその教訓
御柱祭では過去に事故が発生したこともあります。これを教訓に、安全対策は年々強化されており、参加者全体の意識向上が図られています。
御柱の歴史と文化的背景
歴代の御柱祭の変遷
記録が残る限り、御柱祭は1000年以上の歴史を誇り、時代の流れとともに様々な形に変化しながらも、その根底にある精神や信仰は今なお力強く受け継がれています。
この長い歴史の中では、戦争や災害、社会情勢の変化といった外的な要因によって、やむを得ず延期されたり、規模を縮小して実施された年も少なくありませんでした。
しかし、こうした困難の中でも御柱祭は決して完全に中止されることなく、地域の人々によって守られ続けてきました。
それは単なる伝統行事としてではなく、諏訪の人々にとって神とのつながりを再確認し、地域の結束を強めるための欠かすことのできない神事であるからです。
どんな時代でも行われ続けてきた御柱祭は、地域の強い信念と信仰心を象徴する存在なのです。
本殿と御柱祭の関係性
御柱は神の宿る「本殿」を囲むように建てられます。これは神聖な空間を物理的に示すとともに、外敵から守る結界としての役割もあります。
御柱祭に関するよくある誤解
御柱祭はその豪快な曳行や木落としといった迫力あるパフォーマンスが注目を集めることが多いですが、実際には神聖で厳粛な神事としての側面が非常に重要です。
表面的な賑わいや観光要素ばかりに目を奪われてしまうと、この祭りが本来持つ宗教的意義や地域社会との深いつながりを見落としてしまう危険があります。
御柱を曳く行為には、神への奉仕という意味が込められており、参加者はその神聖さを自覚しながら臨む必要があります。
したがって、観光客として参加する際にも、信仰の場であることを理解し、地域の伝統や価値観を尊重する姿勢が求められます。
地元の人々が何世代にもわたり受け継いできたこの神事の重みを感じながら参加することで、より深く意義ある体験となるでしょう。
諏訪大社の役割と御柱祭の関係
諏訪大社の神事の流れ
諏訪大社では年間を通じて様々な神事が行われますが、御柱祭はその中でも最も重要な儀式とされています。
神木の選定から建て付けまで、綿密な計画と準備が必要です。
上社と下社の御柱祭の違い
上社(本宮・前宮)と下社(春宮・秋宮)では御柱祭の形式に若干の違いがあります。たとえば木落としの場所や儀式の進行に地域性が表れています。
神社を支える氏子の存在
氏子とは、神社を支え、地域の神事や祭礼を運営・維持していく役割を担う地域の人々のことを指します。
氏子は単に神社の支援者というだけでなく、信仰と伝統を受け継ぎ、地域文化の継承者として重要な存在です。
御柱祭においても、氏子の存在は欠かすことができません。祭りの準備段階から、御柱の伐採、曳行、安全管理、儀式の進行に至るまで、あらゆる場面で氏子たちの力が発揮されます。
また、世代を超えた協力体制が自然と築かれており、親から子へ、そして孫へと知識や技術、精神が伝えられていく様子は、地域の絆と誇りを象徴しています。
若い世代がその役割を学び、受け継いでいくことで、御柱祭は今後も力強く続いていくことでしょう。
御柱祭における青少年の参加促進
若者が知っておくべき御柱祭の魅力
若者にとって、御柱祭は地元の歴史や文化を学ぶ貴重な機会です。身体を動かし、仲間と協力しながら伝統を体験することで、強い誇りと責任感を育みます。
次世代への伝承方法
学校教育や地域のワークショップなどを通じて、御柱祭の意義や歴史が伝えられています。実際に行事に関わることで、体験を通じた学びが深まります。
参加することの意義
御柱祭への参加は、単に祭りを楽しむだけでなく、地域の一員としての意識を高める行動です。特に若者の積極的な関与が、未来の御柱祭を支える力となります。
御柱祭の観光資源としての可能性
地域活性化に向けた取組み
御柱祭は観光資源としても大きな可能性を秘めています。地元の特産品や文化体験と組み合わせることで、地域の経済活性化に繋げる取り組みが進められています。
諏訪地域の観光名所と御柱祭
御柱祭と合わせて訪れたい名所としては、諏訪湖や高島城、上諏訪温泉などがあります。観光と神事を組み合わせることで、多面的な魅力を提供しています。
外部からの参拝者の声
全国から訪れる参拝者たちは、御柱祭の迫力と地域の温かさに感動し、リピーターになる人も少なくありません。祭りを通じて地域との深いつながりを感じる人も多いです。
御柱祭を支える地域の人々
地区ごとの特色と役割
各地区は、独自の伝統と工夫を持って御柱祭に臨みます。曳き方や装束、掛け声などにその地域性が現れます。
氏子の責任と奉仕の精神
御柱祭は氏子たちの奉仕精神によって支えられています。神事を成功させるために、長期間にわたる準備と協力が必要です。
地域のつながりの重要性
御柱祭を通して地域住民の絆が深まり、世代を超えたつながりが育まれます。祭りが終わった後も、その関係は地域の力として残り続けます。